The “lower world” and earthbound spirits
人類の救世主、神の子イエス・キリストが〝天へ召される者は下界からも選ばれる〟と述べていることについて考察してみたい。下界に見出されるのみならず、その場において天に召されるという。
その〝下界から選ばれる者〟はいずこに住む者を言うのであろうか。これにはまずイエスが〝下界〟という用語をいかなる意味で用いているかを理解しなければならない。
この場合の下界とはベールの彼方においてとくに物質が圧倒的影響力を持つ界層のことを指し、その感覚に浸る者は、それとは対照的世界すなわち、物質は単に霊が身にまとい使用する表現形体に過ぎぬことを悟る者が住む世界とは、霊的にも身体的にも全く別の世界に生活している。
それ故、下界の者と言う時、それは霊的な意味において地上に近き界層に居る者を指す。時に地縛霊と呼ぶこともある。肉体に宿る者であろうと、すでに肉体を棄てた者であろうと、同じことである。
身は霊界にあっても魂は地球に鎖でつながれ、光明の世界へ向上して行くことが出来ず、地球の表面の薄暗き界層にたむろする者同士の間でしか意志の疎通が出来ない。完全に地球の囚われの身であり、彼らは事実上地上的環境の中に存在している。
さてイエスはその〝下界〟より〝選ばれし者〟を天界へ召されたという。その者たちの身の上は肉体をまとってはいても霊体によって天界と疎通していたことを意味する。その後の彼らの生活態度と活躍ぶりを見ればその事実に得心が行く。
悪のはびこる地上をやむを得ぬものと諦めず、悪との闘いの場として厳然と戦い、そして味方の待つ天界へ帰って行った彼ら殉教者の不屈の勇気と喜びと大胆不敵さは、その天界から得ていたのであった。そして同じことが今日の世にも言えるのである。
これとは逆に地上の多くの者が襲われる恐怖と不安の念は地縛霊の界層から伝わって来る。その恐怖と不安の念こそがそこに住む者たちの宿業なのである。肉体はすでに無く、さりとて霊的環境を悟るほどの霊覚も芽生えていない。が、
それでも彼らはその界での体験を経て、やがては思考と生活様式の向上により、それに相応しい霊性を身につけて行く。
かくて人間は〝身は地上に在っても霊的にはこの世の者とは違うことが有り得る〟という言い方は事実上正しいのである。
これら二種類の人間は、こちらへ来ればそれ相応の境涯に落着くのであるが、いずれの場合も自分の身の上については理性的判断による知識はなく、無意識であったために、置かれた環境の意外性に驚く者が多い。
このことを今少し明確にするために私自身の知識と体験の中から具体例を紹介してみよう。
曽て私は特別の取り扱いを必要とする男性を迎えに派遣されたことがある。特別というのは、その男は死後の世界について独断的な概念を有し、それに備えた正しく且つ適切な心掛けはかくあるべしとの思想を勝手に抱いていたからである。
地球圏より二人の霊に付き添われて来たのを私がこんもりとした林の中で出迎えた。二人に挟まれた格好で歩いて来たが、私の姿を見て目が眩んだのか、見分けのつかないものを前にしたような当惑した態度を見せた。
私は二人の付き添いの霊に男を一人にするようにとの合図を送ると、二人は少し後方へ下がった。男は始めのうち私の姿がよく見えぬようであった。そこで、こちらから意念を集中すると、ようやく食い入るように私を見つめた。
そこでこう尋ねてみた。「何か探しものをしておられるようだが、この私が力になってさしあげよう。その前に、この土地へお出でになられてどれほどになられるであろうか。それをまずお聞かせ願いたい。」
「それがどうもよく判りません。外国へ行く準備をしていたのは確かで、アフリカへ行くつもりだったように記憶しているのですが、ここはどう考えても想像していたところではないようです。」
「それはそうかも知れない。ここはアフリカではありません。アフリカとはずいぶん遠く離れたところです。」
「では、ここは何という国でしょうか。住んでいる人間は何という民族なのでしょうか。先ほどのお二人は白人で、身なりもきちんとしておられましたが、これまで一度も見かけたことのないタイプですし、書物で読んだこともありません。」
「ほう、貴殿ほどの学問に詳しい方でもご存知ないことがありますか。が、貴殿もそうと気づかずにお読みになったことがあると思うが、ここの住民は聖人とか天使とか呼ばれている者で、私もその一人です。」
「でも・・・・・・」彼はそう言いかけて、すぐに口をつぐんだ。まだ私に対する信用がなく、余計なことを言って取り返しのつかぬことにならぬよう、私に反論するのを控えたのである。
何しろ彼にしてみればそこは全くの見知らぬ国であり、見知らぬ民族に囲まれ、一人の味方もいなかったのであるから無理もなかろう。
そこで私がこう述べた。「実は貴殿は今、曽てなかったほどの難問に遭遇しておられる。これまでの人生の旅でこれほど高くそして部厚い壁に突き当たったことはあるまいと思われます。これから私がざっくばらんにその真相を打ち明けましょう。
それを貴殿は信じて下さらぬかも知れない。しかし、それを信じ得心が行くまでは貴殿に心の平和は無く、進歩もないでしょう。
貴殿がこれより為さねばならないことは、これまでの一切の自分の説を洗いざらいひっくり返し裏返して、その上で自分が学者でも科学者でもない、知識の上では赤子に過ぎないこと、この土地について考えていたことは一顧の価値もない──つまり完全に間違っていたことを正直に認めることです。
酷なことを言うようですが、事実そうであれば致し方ないでしょう。でも私をよく見つめていただきたい。私が正直な人間で貴殿の味方だと思われますか、それともそうは見えぬであろうか。」
男はしばし真剣な面持ちで私を見つめていたが、やがてこう述べた。「あなたのおっしゃることは私にはさっぱり理解できませんし、何か心得違いをしている狂信家のように思えますが、お顔を拝見した限りでは真面目な方で私の為を思って下さっているようにお見受けします。で、私に信じて欲しいとおっしゃるのは何でしょうか。」
「〝死〟についてはもう聞かされたことでしょう。」
「さんざん!」
「今私が尋ねたような調子でであろう。なのに貴殿は何もご存知ない。知識というものはその真相を知らずしては知識とは言えますまい。」
「私に理解できることを判り易くおっしゃってください。そうすればもう少しは吞み込みがよくなると思うのですが・・・・・・」
「ではズバリ申し上げよう。貴殿はいわゆる〝死んだ人間〟の一人です。」
これを聞いて彼は思わず吹き出し、そしてこう述べた。
「一体あなたは何とおっしゃる方ですか。そして私をどうなさろうと考えておられるのでしょうか。もし私をからかっておられるだけでしたら、それはいい加減にして、どうか私を行かせてください。この近くにどこか食事と宿を取る所がありますか。少しこれから先のことを考えたいと思いますので・・・・・・」
「食事を取る必要はないでしょう。空腹は感じておられないでしょうから・・・・・・宿も必要ありません。疲労は感じておられないでしょうから・・・・・・それに夜の気配がまるでないことにお気づきでしょう。」
そう言われて彼は再び考え込み、それからこう述べた。
「あなたのおっしゃる通りです。腹が空きません。不思議です。でもその通りです。空腹を感じません。それに確かに今日という日は記録的な長い一日ですね。わけが分かりません。」
そう言って再び考え込んだ。そこで私がこう述べた。
「貴殿はいわゆる死んだ人間であり、ここは霊の国です。貴殿は既に地上を後にされた。
ここは死後の世界で、これよりこの世界で生きて行かねばならず、より多く理解して行かねばならない。まずこの事実に得心が行かなければ、これより先の援助をするわけには参りません。しばらく貴殿を一人にしておきましょう。
よく考え、私に聞きたいことがあれば、そう念じてくれるだけで馳せ参じましょう。それに貴殿をここまで案内してきた二人が何時も付き添っています。何なりと聞かれるがよろしい。答えてくれるでしょう。
ただ注意しておくが、先ほど私の言い分を笑ったような調子で二人の言うことを軽蔑し喋笑してはなりません。謙虚に、そして礼儀を失いさえしなければ二人のお伴を許しましょう。
貴殿はなかなか良いものを持っておられる。が、これまでも同じような者が多くいましたが、自尊心と分別の無さもまた度が過ぎる。それを二人へ向けて剥き出しにしてはなりませんぞ。
その点を篤と心してほしい。と言うのも、貴殿は今、光明の世界と影の世界との境界に位置しておられる。そのどちらへ行くか、その選択は貴殿の自由意志に任せられている。神のお導きを祈りましょう。それも貴殿の心掛け一つに掛かっています。」
そう述べてから二人の付き添いの者に合図を送った。すると二人が進み出て男のそばに立った。そこで三人を残して私はその場を離れたのであった。
──それからどうなりました。その男は上を選びましたか下を選びましたか。
その後彼からは何の音沙汰もなく、私も久しく彼のもとを訪れていない。根がなかなか知識欲旺盛な人間であり、二人の付き添いがあれこれ面倒を見ていた。が、
次第にあの土地の光輝と雰囲気が慣染まなくなり、やむなく光輝の薄い地域へと下がって行った。そこで必死に努力してどうにか善性が邪性に優るまでになった。その奮闘は熾烈にしてしかも延々と続き、同時に耐え難く辛き屈辱の体験でもあった。
しかし彼は勇気ある魂の持ち主で、ついに己れに克った。その時点において二人の付き添いに召されて再び始めの明るい界層へと戻った。
そこで私は前に迎えた時と同じ木蔭で彼に面会した。その時は遥かに思慮深さを増し、穏やかで、安易に人を軽蔑することもなくなっていた。私が静か見つめると彼も私の方へ目をやり、すぐに最初の出会いの時のことを思い出して羞恥心と悔悟の念に思わず頭を下げた。私をあざ笑ったことをえらく後悔していたようであった。
やがてゆっくりと私の方へ歩み寄り、すぐ前まで来て跪き、両手で目をおおった。嗚咽で肩を震わせているのが判った。
私はその頭に手を置いて祝福し、慰めの言葉を述べてその場を去ったのであった。こうしたことはよくあることである。 ♰
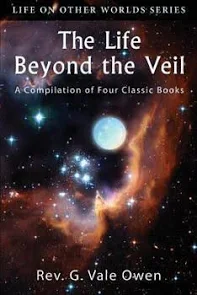
No comments:
Post a Comment